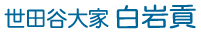所有不動産記録証明制度とは?2026年に始まる本制度の利用方法とは
【2026年スタート】所有不動産記録証明制度の概要
来年2026年に、全国にある不動産が従来よりも調べやすくなる制度がスタートすることをご存じでしょうか。この制度は「所有不動産記録証明制度」と呼ばれます。本章ではこの制度の概要について詳しく解説します。
同一所有者の不動産を全国で調査できる制度
本制度は、不動産に登記されている所有者の情報を利用するものです。所有者の氏名・住所が一致していれば、遠く離れている不動産であっても一括で検索できるようになります。
たとえば、亡くなられたご家族の不動産を相続時に調べたい場合、所有者のご出身地にある不動産がなかなか見つからず、苦労される相続人が多くおられました。しかし、新しい制度を利用すれば、簡単に見つかるようになるのです。
利用方法
本制度は2026年2月以降に運用が開始される見込みです。利用方法は未定ですが、すでに法務大臣が指定する登記所にて取得できることが定められているため、法務局にて検索や郵送での情報取り寄せが可能になると考えられます。
本制度を利用できる方は以下です。
| ・不動産を所有している本人(不動産名義人) ・不動産を所有している本人の法定代理人(親権者や成年後見人など) ・不動産を所有している本人から依頼された代理人(弁護士や司法書士など) ・生前に不動産を所有していた本人の相続人 |
なぜ本制度は整備されたか
後述しますが、これまで不動産を調べるにあたっては一括で調べる制度がなく、不動産がある現地を管轄する法務局で登記簿を取得したり、各自治体に依頼し調査を行う必要がありました。しかし、相続登記が義務化されており、より相続登記をスムーズに進めるためにも所有者ベースで全国にある不動産を調べる方法が模索されていました。
今後考えられる所有不動産記録証明制度の活用方法
今後不動産は現在よりも調べやすくなりますが、実際に本制度はどのような場面で活躍すると考えられるでしょうか。主な場面は以下です。
生前からの相続・贈与対策
①相続対策
過去の相続によって、亡くなった父母などから遠方にある不動産を取得している方は少なくありません。しかし、配偶者や子は現地に足を運んだことがなく、相続で取得している事実もあまりご存知ではないケースも多く散見されます。よくあるケースとしては、地方にある実家周辺の不動産を取得した事実を、都市部に暮らす配偶者や子は全く知らなかった、というものです。
今後ご自身で現在所有している不動産を調べ、家族に話しておくことで相続対策が以前よりもスムーズになるでしょう。遺言書を作る際にも便利です。
②贈与対策
所有している不動産を早めに誰かに贈与したい場合、どこにどのような不動産を所有しているか把握する必要があります。贈与を進める際にも、本制度の活用は有効でしょう。
相続登記・相続税申告漏れを防ぐ
相続人は、被相続人(亡くなられた家族)の遺産を調査し、漏れなく相続手続きを進める必要があります。しかし、遠方にある不動産はこれまで把握漏れが起きることが決して少なくなく、相続登記や相続税申告漏れが起きることがありました。
しかし、相続開始後の遺産調査の中で、本制度を利用すれば相続すべき不動産の情報がすぐに把握できます。
また、遺産分割協議時に不動産を確実に把握し、相続人を確定させる際にも本制度は便利でしょう。
その他
この他に、成年後見人をはじめとする法定代理人が不動産を調査したり、依頼を受けた代理人が不動産を調査することも考えられます。
これまでは不動産をどのように調べていた?
では、これまでは不動産を調べる方法としてどのようなものがあったのでしょうか。2025年内は従来の方法で調べる必要があるため、ぜひ下記をご参考ください。
固定資産税納税通知書
毎年4月頃に、不動産が立地する住所を管轄する各自治体から「固定資産税納税通知書」が発送されています。この通知書には、固定資産税が課税されている不動産が記載されているため、相続時などに不動産を特定するためにも役立っています。
※注意点
この通知書には非課税の不動産が記載されていませんし、遠方から届く通知書が見落とされやすいという問題点があります。また、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税通知が行われるため、1月2日以降に取得した不動産は本年の通知書には記載されません!
登記済権利証・登記識別情報
不動産を取得する時には「登記済権利証」を受領します。また、2005年に登記済権利証」からデジタル化によって登記識別情報」が発行されています。これらも不動産の所有を特定する好材料です。
※注意点
随分昔に不動産を取得しているケースでは、登記済権利証が見つからないというケースも散見されます。
名寄帳
非課税の不動産の情報も調べる場合は「名寄帳」を取得します。固定資産税納税通知書には記載されていない不動産も見つかるため、特に相続時には欠かせない調査方法です。市区町村ごとに記載されているため、不動産が立地する住所を管轄している自治体から取り寄せます。
※注意点
自治体によっては名寄帳を発行していない場合があります!この場合、自治体の相談し別の書類を発行してもらう必要があります。たとえば、愛知県名古屋市では本年4月まで名寄帳は発行しないため、以下のようにアナウンスされています。
| “引用 名古屋市役所 Q.名寄帳(なよせちょう)の写しの取得方法を知りたい。 名古屋市においては、納税義務者本人に対して課税資産を一覧にした課税明細書を毎年4月に納税通知書に同封して送付していることを考慮して、名寄帳の写しの交付を行っていません。なお、課税明細書を紛失した場合は、再交付することができますので、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。“ |
その他
この他、農協や私道利用に関する通知から不動産の所有が判明するケースもあります。過去の相続時に取得した不動産がわからない場合、当時の遺産分割協議書を確認することもおすすめです。
遠方の不動産は早めに相続対策を始めよう
今後本制度の導入によって、不動産が調べやすくなります。そこで、絶好の機会を活かして、早めの相続対策を開始することがおすすめです。ただし、利用までは1年程度先となるため、相続対策が気になる場合は現行の調査方法を使って不動産を調べましょう。では、早めの不動産調査は相続対策にどのような効果があるでしょうか。
空き家問題の発生を防ぐ
当サイトでもすでに紹介済ですが、不動産は現在深刻な「空き家問題」に直面しています。早めに誰が相続するのか、不要ならいつ処分するのか話し合いを開始するためにも、特に現在のお住まいから遠方にある不動産を取得している場合には、この機会に空き家とならないように話し合いを家族間で重ねておくことがおすすめです。
関連記事:空き家相続時の注意点|特例措置や相続放棄を詳しく解説
有効活用を検討できる
ご自身でも把握しきれていない不動産がある場合、早めに所有状況を把握することで、有効活用できる不動産が見つかることもあります。駐車場や民泊など、活用できる不動産を活かせば、収入が増えることになります。有効活用できる不動産は贈与にもメリットがあり、家族の資産形成にも大きく貢献してくれます。
関連記事:相続した家を有効活用!おすすめ事例や節税のポイントを解説
まとめ
本記事では2026年に開始される予定の「所有不動産記録証明制度」について、制度の概要や利用方法を中心に詳しく解説しました。不動産を相続より前に調べておくことは、遺言書の作成や相続・贈与対策にもおすすめです。ただし、利用開始までまだ時間があるため、早期に対策を開始したい場合はお気軽に当事務所にお尋ねください。