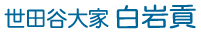【相続人に認知症の方がいたら】不動産相続はどうなる?
相続人に認知症の方がいた場合の相続手続き
相続手続きを開始した際に、もしも相続人の中に「認知症」を患っている方がいたら、手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
認知症とは、脳の神経細胞の働きが低下し、記憶力や判断力などの認知機能も下がることで日常生活に支障をきたす状態を指します。本章では相続人に認知症の方がいた場合の相続手続きについて解説します。
遺言書がある場合
被相続人が生前「遺言書」を残していた場合、相続人への遺産の分配については遺言書の記載内容に沿って行うことができます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、以下2つの方法で遺産分割を進める必要があります。
①法定相続分どおりに遺産分割を行う
法定相続分どおりに遺産分割を行うため成年後見人は不要です。
しかし、現金・有価証券・不動産などを含んだ遺産をすべて法定相続分どおりに分けるため、不動産が共有名義となってしまいます。
②認知症の相続人に成年後見人を付けた上で遺産分割協議を行う
認知症の相続人に成年後見人を付けた上で、遺産分割協議を行う方法もあります。この場合、認知症の方に代わって成年後見人が協議に参加するため①と比較するとより柔軟な話し合いが可能です。
相続放棄をさせたい場合
被相続人に高額の債務がある等の事情で、認知症がある相続人に「相続放棄してほしい」と考える家族もいるでしょう。しかし、認知症がある相続人は、自身で相続放棄を行うことができません。そのため、上記の②と同じように成年後見人を付けた上で、相続放棄を進める必要があります。
成年後見人は本当に認知症のある相続人が、相続放棄で不利益を被らないのか、入念に調査した上で放棄を進めることが必要です。
【結論】認知症の相続人には多くのケースで成年後見人が必要
相続手続きの中で、遺言書がないケースでは認知症の相続人には成年後見人が必要です。法定相続分どおりの相続には成年後見人は不要ですが、遺産の内容によっては共有状態の不動産を抱えてしまうため、相続手続き後も重い負担が相続人全員に残されてしまいます。
特に不動産が多い場合は成年後見人の選任を行った上で、遺産分割協議を行う方が良いでしょう。
成年後見人制度とは|相続時の制度利用のメリット・デメリット
成年後見人制度とは、一体どのようなものでしょうか。この章では制度の概要について簡潔に触れながら、相続時における制度利用のメリット・デメリットを解説します。
成年後見人は原則途中でやめられない
成年後見制度を開始するためには、家庭裁判所に選任の申立てを行う必要があります。家庭裁判所の判断で成年後見人が認められた場合、原則途中で成年後見制度の利用終了は認められません。たとえば、相続手続き時に必要で選任してもらい、無事に手続きが終わったとしても、その後も成年後見人が継続して付けておく必要があります。
柔軟な遺産分割協議はできない
相続手続き時に成年後見人を選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらっても、成年後見人の立場はあくまでも「成年被後見人」を不利益な相続から守るものです。
その他の相続人にのみ有利な遺産分割協議に同意するわけではありません。原則として、法定相続分程度の遺産は確保せざるを得ないため、柔軟な遺産分割協議に応じてくれるわけではないと知っておきましょう。
成年後見人の選任に時間を要する
相続手続きは、主に以下の期限を意識して進める必要があります。
・相続放棄、限定承認
・相続税申告
・相続登記 など
特に相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内」に行う必要があります。そのため、認知症がある相続人が相続放棄をするためには迅速に成年後見人の選任申立てを行う必要がありますが、選任には時間がかかるケースもあります。
時間がかかりそうな場合、あらかじめ相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所に対して申立てしておく必要があります。
参考URL裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長
成年後見人のメリット・デメリット
成年後見人は相続手続き時以外にも必要に応じて選任しておく必要がありますが、メリット・デメリットがある制度です。成年被後見人を守る効果は高いですが、その一方で報酬が必要などのデメリットがあります。簡潔にご紹介しますので、ご一読ください。
| 成年後見制度の主なメリット | 成年後見制度の主なデメリット |
| ①本人の保護: 判断能力が不十分な方の財産や権利を守り、不利益な契約や詐欺被害から保護する ②財産管理の代行: 預貯金や不動産の管理を任せられる ③契約行為のサポート: 介護施設への入所契約や医療契約、不動産の売買契約などを代行できる ④専門家のサポート: 弁護士や司法書士などの専門家が後見人となることで、法的な手続きや専門知識が必要な場合に適切な対応ができる | ①費用: 後見人への報酬や、申立てにかかる費用、専門家への相談費用などがかかる ②手続きの煩雑さ: 家庭裁判所への申し立てや、後見人選任後の定期的な報告など、手続きに手間と時間がかかる ③後見人の選任: 家庭裁判所が後見人を選任するため、親族が後見人になれるとは限らない ④財産の活用制限: 後見人は本人の財産を保護することが第一であるため、自由な投資や贈与などはできない。 |
不動産がある場合の相続には特に注意が必要
被相続人の財産に多くの不動産がある場合、認知症の方が相続人にいると手続きが複雑化しやすいため注意が必要です。
・法定相続分どおりに分割する場合
不動産を法定相続分どおりに分割する場合、民法で定められた持ち分に沿って相続登記を行います。不動産を複数名で共有状態にすると、売却が複雑になるほか、次に発生する相続でさらに共有者が増えてしまうリスクがあります。また、売却時にも認知症の相続人の同意が必要です。しかし、判断能力上同意ができないため売却のタイミングで成年後見人が必要となります。
・成年後見人がいる場合も注意
成年後見人を選任している場合も、認知症の相続人について「法定相続分相当」は財産を取得する必要があるため、不動産がある場合は代償金を支払うなどの対策が必要です。
ただし、代償金を支払えば不動産の共有化は避けられ、売却や資産運用もスムーズです。
成年被後見人は法定相続分以上の相続が必要
認知症がある方に成年後見人が付くと「成年被後見人」と呼ばれます。成年被後見人にとって不利な遺産分割にならないように、原則として相続時には「法定相続分以上」の遺産を取得する必要があります。認知症だからといって財産を渡さなかったり、過剰に遺産を減らすことはできません。
柔軟な不動産の取得、売却が進まない可能性がある
認知症の方がいる場合、すでにご説明のとおり不動産相続が複雑化するおそれがあります。柔軟な不動産の取得が遺産分割協議を行っても難しいケースが多く、売却も思うようにできない場合が多いでしょう。成年後見制度利用下での不動産相続はデメリットが多いと知っておきましょう。
まとめ 認知症のご家族がいる場合は生前から相続対策を
本記事では認知症の方がいる相続について、主に不動産相続の視点から詳しく解説しました。日本は高齢化社会が進んでおり、認知症を患われる方も決して少なくありません。相続時に認知症の方が相続人の中におられると、成年後見人が必要となることが多く、できれば生前から相続対策を行っておくことが重要です。
遺言書があれば安全に相続手続きが進められるほか、あらかじめ不安を感じる不動産は贈与や売却を進めることも検討しましょう。