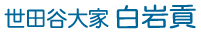不動産の共有名義はリスクだらけ|相続時に避けるべき理由
相続時の不動産|「とりあえず共有」は危険!
相続が始まり、相続人全員で不動産を含む遺産を誰が、どのように相続するのか協議を重ねても、話し合いがまとまらないケースは少なくありません。遺産分割協議がまとまらないと、預貯金口座の解約や車の名義変更、相続税申告などにも影響してしまうため「とりあえず不動産を共有化する」ことで、遺産分割協議の終結を検討する方もいるでしょう。
しかし、相続時の不動産をとりあえず共有にしてしまうことで、後々に大きなトラブルに発展する可能性があります。その理由は以下です。
売却や増改築等がしにくくなる
1つの建物や土地を複数の相続人で共有化してしまうと、売却をする際にも共有者全員の同意が必要になります。また、増改築などのリフォームを検討する際も同様です。
不動産を賃貸化したい場合など、その他にも同意が必要なケースがありますので以下をご参考ください。
| 共有している不動産に行いたいこと | 左記実施の前に必要な同意内容 |
| 保存行為 (共有物の修理など) | 不要 |
| 管理行為 (共有物を貸すこと) | 共有者の持分価格の過半数の同意 |
| 軽微な内容の変更行為 (簡単な修繕) | 共有者の持分価格の過半数の同意 |
| 軽微な内容以外の変更行為 (共有物の売却、増改築など) | 共有者全員の同意 |
次の相続の発生で共有者が増える
共有者のどなたかが亡くなってしまうと、その方の相続が開始されます。次の世代の相続人が複数いた場合は、共有者が増えてしまうのです。
たとえば、共有者がAとBの2名だったと仮定しましょう。Bが亡くなり、相続人にC、Dが居た場合には、A・C・Dの3名が共有者となります。
もしもAと新たな相続人であるC・Dの交流が盛んではない場合、売却や賃貸時の話し合いも上手く進まなくなるおそれがあります。
一部の共有部分が売却されてしまう
不動産をとりあえず共有化しておくと、他の共有者が持分を売却してしまうというおそれもあります。
たとえば、共有状態の不動産をお持ちの方の中には、ある日突然「他の共有者が持分を売却した」と驚くケースがあります。建物や土地全体を売却する際には共有者全員の同意が要りますが、自分の持分のみを売却する際には、別の共有者の同意を得る必要はありません。
近年は共有持分の購入を積極的に取り扱う不動産会社も増えており、ある日全く関わりがない第三者が共有者として現れることがあるのです。共有部分を買い取った不動産会社は再活用に向けて売却等を交渉してくる傾向があるため、売却せずに残っている共有者にとっては大きなストレスとなるおそれがあります。
滞納によって連帯納付義務が発生する
不動産を共有化すると、発生する固定資産税は代表者宛に固定資産税納付書が発送されます。共有者が分担して納税するのではなく、代表者がまとめて支払うしくみです。
しかし、代表者1人に納付義務があるわけではありません。地方税法では、不動産が共有化されている場合は、連帯納付義務があるとしており、もしも滞納してしまったらその他の共有者が納税する義務があります。
あまり多い事例ではないですが、「代表者に自分の分の固定資産税を払っていたのに、滞納の通知が来た」というケースもあります。
参考URL 東京都 小平市 共有名義の固定資産の課税について
共有名義にメリットなし!どうやって不動産を相続する?
不動産を共有名義の状態にしておくと、上記で紹介したようなデメリットに直面する可能性があります。できれば相続の開始後に不動産の扱いについては共有化を避ける解決を目指すことがおすすめです。では、不動産はどのように相続するとよいでしょうか。
不動産相続の基本的な流れはぜひ以下記事もご一読ください
あわせて読みたい 2024年最新版!不動産相続の基本的な流れや必要書類とは
デメリットも踏まえて遺産分割協議をする
今回ご紹介のように、共有状態のままで不動産を所有するとデメリットに直面しやすくなります。そのため、面倒に感じても遺産分割協議の段階で本当に共有状態にしてよいのか慎重に話し合いを重ねましょう。どうしても共有状態にしなければ遺産分割協議がまとまらない場合は、近い将来共有状態の解消はできるかどうか、改善の余地を残した話し合いを目指すことも大切です。
相続の段階で3つの分割方法で解消を目指す
遺産分割協議中には、以下3つの方法のうちいずれかを選択すれば、共有状態を避けられます。
①現物分割
土地を分筆し、それぞれが取得する方法。ただし、分筆できない土地もある。また、分筆により土地の評価が下がる可能性もある。
②代償分割
誰かがまとめて不動産を取得する。不動産を取得した相続人は、取得しなかった相続人へ代償金を支払う。
③換価分割
不動産を売却して得られた売却代金を、相続人間で分割する。現金を得られるため不公平感がないが、不動産は失うことになる。
いずれの方法にもメリット・デメリットはあります。慎重に話し合った上で決めましょう。
生前から所有者の家族と協議をしておく
不動産を所有しているご家族がいる場合、生前の段階から不動産を誰が今後管理していくべきか、話し合いを重ねることもおすすめです。場合によっては早期の贈与で、不動産を安全に次の世代へと委ねることも考えられます。
また、現時点では贈与が出来なくても、不動産をめぐる話し合いがこじれそうな場合には、あらかじめ所有者が将来に備えて遺言書を作っておくことも検討できるでしょう。
共有名義となっている不動産の解消方法とは
すでに共有名義の状態となっている不動産に悩んでいる場合は、以下の方法で問題の解決が可能です。
共有状態のまま売却を目指す
共有者全員の同意があれば、共有状態の不動産であっても売却は可能です。全員が売主として売却の協議に参加します。売買交渉の段階に入ってからこじれてしまうと、売却が難航してしまうため、あらかじめ全員が意思確認をした上で売買交渉に入ることが大切です。
やむを得ない場合、自己の持分は売却する
共有状態が解消できず、共有持分があることがストレスになっていたり、次の相続に向けて負担を減らしたい場合等のケースでは、自身の共有持分のみを売却する方法も考えられます。次の相続に向けて共有持分を減らしたい場合は、相続手続きを複雑化させないためにも別の共有者への売却が望ましいでしょう。
別の共有者と折り合いが悪かったり、面識に乏しく交渉ができないケースでは、共有持分を買い取ってくれる業者への売却も検討しましょう。
まとめ
本記事では、不動産の共有名義のリスクについて詳しく解説しました。相続時は不動産を巡って対立が起きやすいですが「とりあえず共有」という選択は危険をともないます。次の相続時にかかる負担を減らすためにも、遺産分割協議には代償分割なども検討しましょう。
ただし、共有状態であっても共有者全員の同意があれば売却や賃貸化をすることは可能です。円満な不動産活用は生前・相続開始後のいずれであっても、家族仲良く協議をすることでトラブルが起きにくくなります。