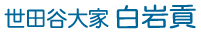なぜ相続税の払い過ぎは起きる?不動産評価の注意点
相続税は払い過ぎる?高額納税が起きるワケ
財務省によると、令和4年度の相続税の課税件数割合は、相続全体の9.6%とされています。平成27年の基礎控除の見直しによって、相続税が課税される人の割合は増加傾向にあるため、誰もが相続時に相続税に直面する可能性があります。時には重い負担となる相続税は「払い過ぎる」ことが多いことはご存知でしょうか。
相続税は税務署や自治体が自動的に計算してくれるものではないため、実は払うべき金額よりも多く支払ってしまうことがあるのです。では、相続税の高額納税が起きる理由とは、どのようなものでしょうか。
参考URL 財務省 相続税の改正に関する資料
多く支払うことで税務調査を避ける
相続税に誤りや虚偽の内容があると判断すると、税務署が「税務調査」を行う可能性があります。税務調査の対象になると追徴を受ける可能性が高いため、相続税申告時には「多く支払う」ことで税務調査を避けようとする税理士がいます。
多く支払っても税務署から知らせは来ない
計算ミスや特例・控除の適用漏れがあったとしても、税務署は「相続税の納め過ぎですよ」と知らせてはくれません。つまり、多く払い過ぎたとしても納税者側がその事実に気付きにくいのです。
不動産評価が難しく高額になりやすい
相続税が課税される方の多くは、遺産の中に「不動産」を所有しています。不動産は預貯金や株式と比較すると「減額できる要素」が多数あります。しかし、税理士によって評価内容がまるで異なります。同じ土地でも、相続税に強い税理士なら土地を正しく評価し相続税を抑えられます。
一方で、評価に詳しくない税理士が担当したことによって、不動産評価が高く、結果として相続税も高くなるケースもあります。不動産評価は慎重に行わないと、納税者側に大きな不利益となるおそれがあります。
相続時によくある不動産評価の問題とは
相続時には「不動産評価」が相続税に影響することがあります。そこで、この章では相続時によくある不動産評価の問題点を整理し、わかりやすく解説します。
減額要因が見落とされやすい
相続税における不動産評価は、土地と建物を分けて行います。
①土地の評価
土地の評価方法は2つに分けられます。1つは「路線価方式」、もう1つは「倍率方式」です。路線価が設定されている場所の土地は路線価方式で行い、路線価が設定されていない場所の土地は倍率方式で行います。
②建物の評価
建物の評価は固定資産税評価額に評価倍率(1.0)を乗じて算出するため、基本的に固定資産税評価額がそのまま採用されます。なお、賃貸の有無で評価は変動します。
土地の評価については、路線価方式において評価減につながる「調整率」が採用されます。この調整率によって、土地の評価を下げることが可能です。調整率は土地の立地、地形や現在の状態で大きく左右されますが、知識や経験がないと正しい調整率が採用されず、結果として土地の評価が高いまま、納税に至るケースが散見されます。
相続税専門の税理士は意外と少ない
上記のとおり、不動産の中でも土地の評価は計算によって大きく変動します。しかし、相続税における土地の評価の経験が乏しいと、正しく算出できません。日本国内には多数の税理士がいますが、相続税を専門にしている税理士は少ないと言われています。つまり、どの税理士に相談するかによって、相続税が変わってしまう可能性が高いのです。
期限に間に合わせるために多く支払いがち
相続税の申告・納付の期限は「被相続人が死亡したことを知った日から10か月」以内に終える必要があり、一般的には亡くなったその日から10か月以内です。遺産の種類や総額の確定を、葬儀・遺品整理・遺産分割協議などと並行して行う必要があり、相続税申告・納付の期限までは非常にタイトなスケジュールと言えるでしょう。
そこで、安全に相続税を乗り越えるためにも多く支払ってしまう傾向があります。すでに触れたとおり、払い過ぎがあっても原則として税務署は指摘してくれないため、結果として払い過ぎが改善されないままになりがちです。
相続税の払い過ぎに備える|還付の手続きとは
相続税は払い過ぎることがある、ということがわかっていたら、相続税申告や不動産評価にどう対応するべきか悩んでしまう人も多いでしょう。そこで、この章では相続税の払い過ぎに備えるために「還付手続き」の方法をご紹介します。
払い過ぎたら還付金を受け取ることができる
もしも相続税を払い過ぎてしまったとしても、手続きを行えば「還付金」を受け取ることが可能です。ただし、還付金の手続きには期限が設けられており「被相続人が亡くなってから5年10か月以内」に行う必要があります。(申告期限から5年)
更生の請求を行う
還付金を請求するためには「更生の請求」を行います。更正の請求は上記に述べた期限内に行いましょう。手続きの流れは簡潔に以下のとおりです。
1.払い過ぎを確認するために、申告した書類を確認しながら再計算を行う
2.更生の請求書類を作成する
3.更生通知書が税務署から届く(目安として3か月程度)
4.国税還付金振込通知が届く(3から1か月以内程度)
5.還付金が振り込まれる(4から2週間程度)
払い過ぎが認められた場合は税務署へ書類の提出後から、おおよそ5か月以内を目安に還付金が振り込まれます。詳しい手続きや書類については、以下国税庁のリンクからご確認ください。
参考URL 国税庁 B1-27 相続税及び贈与税の更正の請求手続
不動産の相続税の払い過ぎを生前から避けるヒント
不動産の相続税はその他の遺産と比較すると払い過ぎの原因となりやすいため、生前からしっかりと対策を行っておくことがおすすめです。そこで、生前からできる不動産の相続税の払い過ぎを防ぐヒントをご紹介します。
生前から税理士に相談を開始する
相続税を専門とする税理士は少ないため、現在不動産賃貸や事業に関する相談を行っている税理士が、相続に強いとは限りません。そこで、生前から相続税に強い税理士にセカンドオピニオンとしても相談をしてみることがおすすめです。現時点での相続税試算も可能で、贈与や遺言に関するアドバイスも行ってくれる税理士が望ましいでしょう。
生前からコツコツと準備を進めておくことで、家族が相続を迎えた時にも相続税申告がスムーズになります。
還付に関する知識を知っておく
ご紹介のとおり、相続税はもしも払い過ぎたとしても、更生の請求を行うことで還付金が戻ってきます。こうした相続税、相続全般にまつわる知識を早くから知っておくことで、万が一の際にも慌てずに手続きが進められます。
まとめ
本記事では相続税の払い過ぎに焦点を当てて、詳しく解説を行いました。現在不動産を多くお持ちの資産家の方々は、相続を迎える時に何を知っておくべきか悩んでいるのではないでしょうか。
相続税は残されるご家族にとって重い負担となるため、不動産評価や還付金に関する手続き方法などを、早くから学んでおくことがおすすめです。